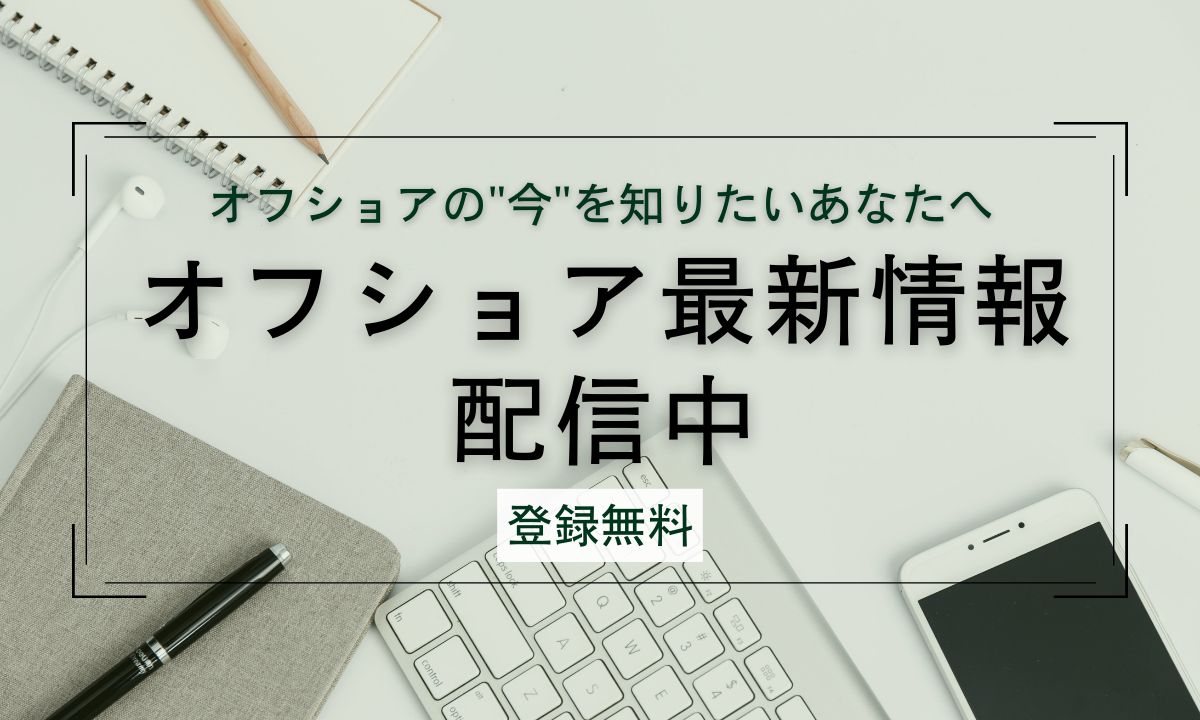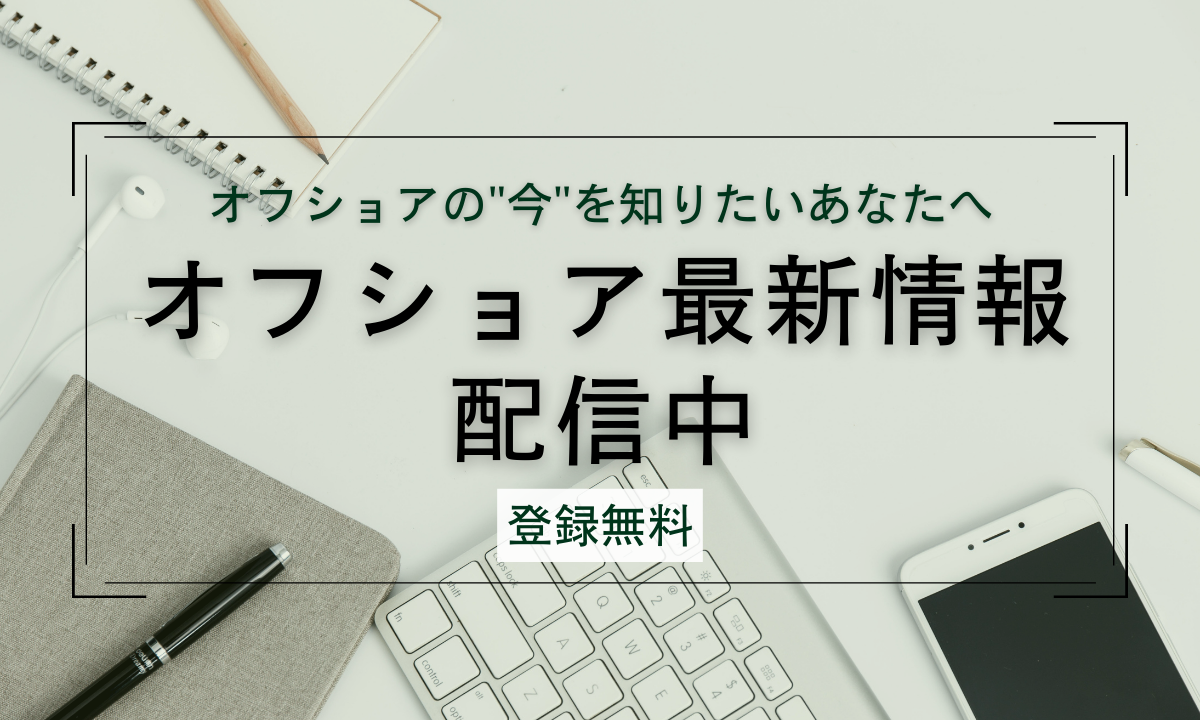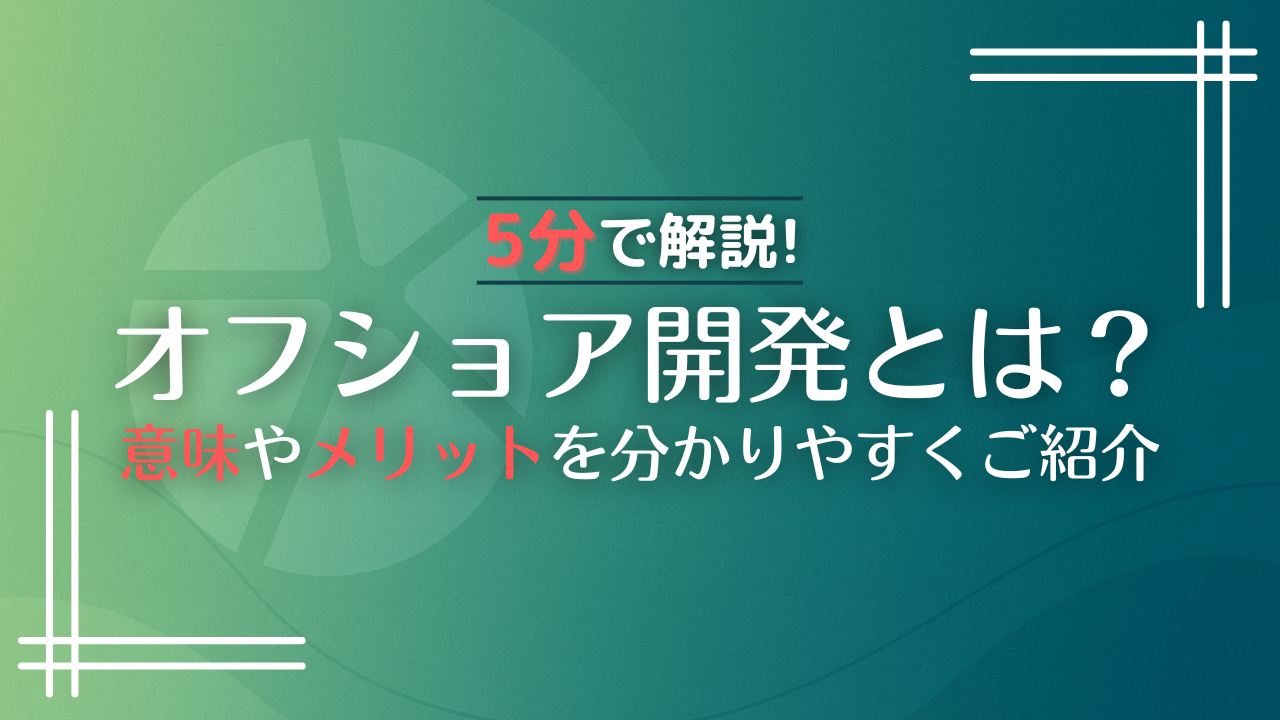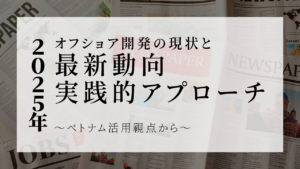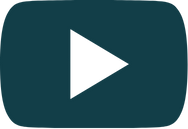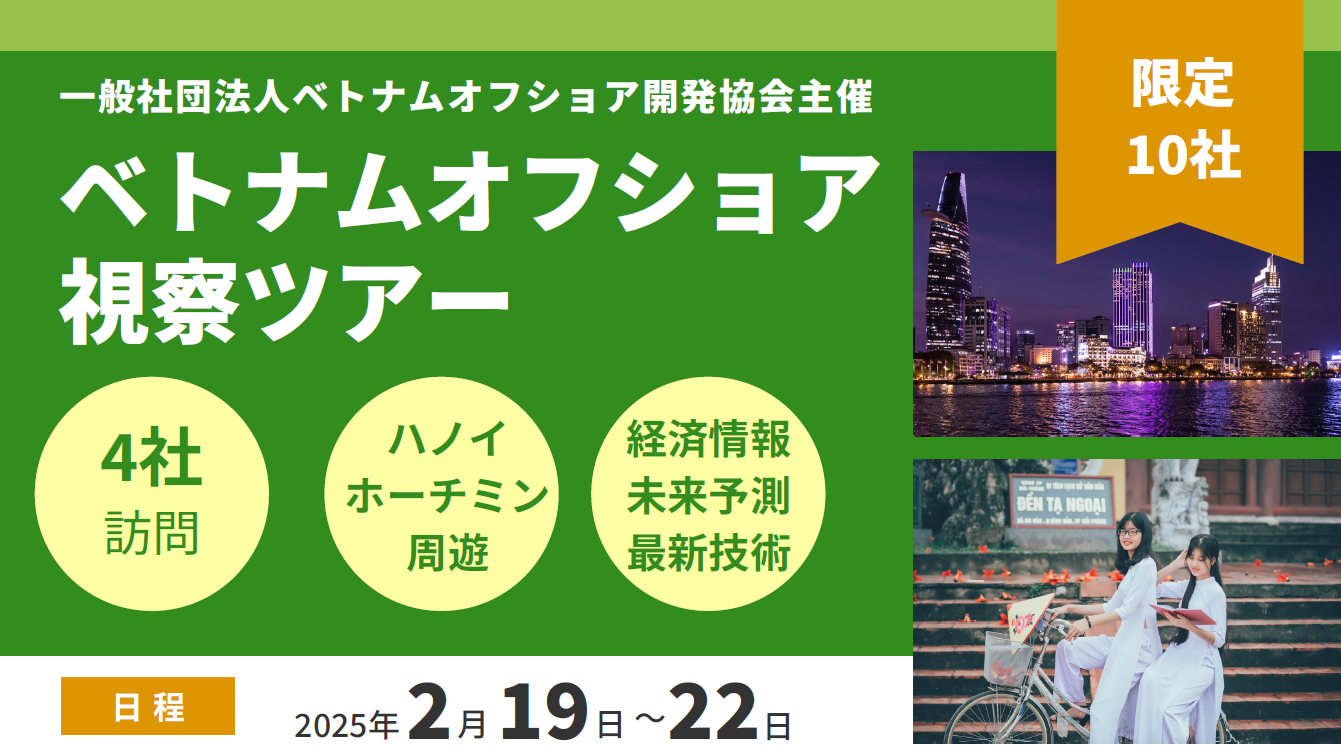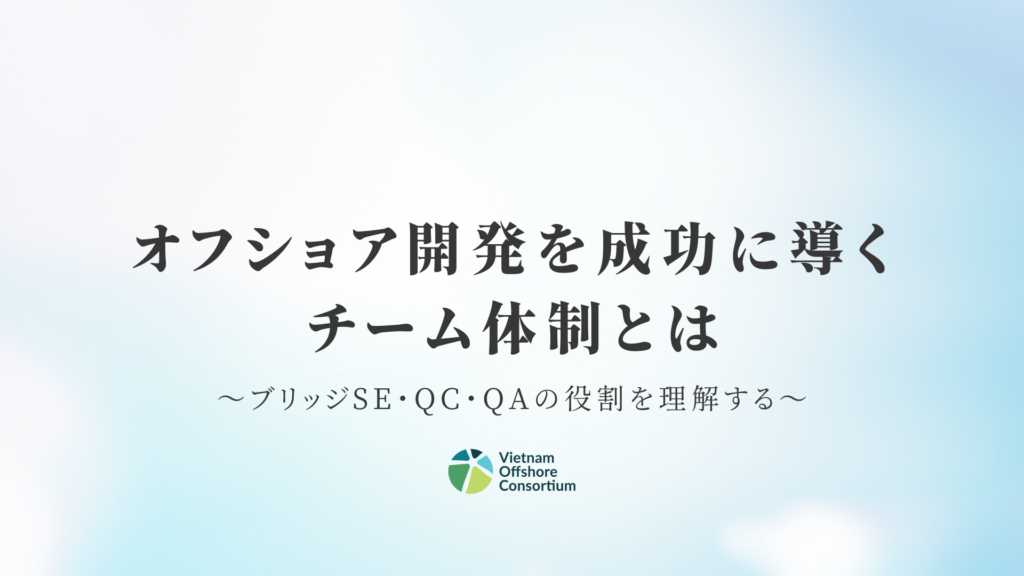
こんにちは。ベトナムオフショア開発協会事務局です。
オフショア開発を検討するとき、「国内開発と同じ体制で進めればいいのでは」と考える企業は少なくありません。
しかし、実際には国内開発では見えにくい“境界”がいくつも存在します。
言語・文化・作業時間・開発プロセスの前提――それらの違いを橋渡ししなければ、プロジェクトはすぐに認識齟齬を起こします。
その境界を埋めるのが、オフショア開発に特有の職種たちです。
本稿では、国内開発には登場しにくいものの、海外チームと連携するうえで欠かせない代表的なメンバーと、その役割の背景を解説します。
この記事はこんな方におすすめです
1.ブリッジSE(BrSE)――文化と要件の翻訳者
オフショア開発を語るうえで欠かせない存在が「ブリッジSE(Bridge System Engineer)」です。
BrSEは単なる通訳ではなく、「ビジネス要求を技術言語に変換し、逆方向にも翻訳するエンジニア」です。
日本側の顧客やPMが語る要件には、しばしば“日本的な曖昧さ”が含まれます。
「普通はこうするよね」「細かい部分は任せる」といった言葉を、現地の開発者がそのまま理解するのは不可能です。BrSEはこうした言葉の背景を読み取り、目的・前提・制約を整理して現地メンバーに伝えます。同時に、現地チームから上がる質問やリスクを日本語で再構成し、意思決定者に報告します。
この“橋渡し”がなければ、進捗は見えていても、成果物の中身がずれていく。
BrSEは単なる翻訳者ではなく、文化の違いによる“認識の歪み”を修正する調整者なのです。
2.BSE(Base SE)またはリードエンジニア――技術の橋渡し役
BrSEが主に言語とマネジメントの橋を担うのに対し、BSE(Base SE)は技術的な橋を担います。
彼らは詳細設計やレビューを中心に、開発者が迷わないよう技術面の方向性を示します。
国内では、経験豊富なSEやチームリーダーが自然とこの役割を果たしますが、オフショアでは技術スタックやフレームワークの理解度、ドキュメント形式の違いが障害になります。
BSEが存在することで、日本の開発標準を現地仕様に落とし込み、設計品質を均一化することが可能になります。
たとえば、設計レビューで「この命名ルールはチーム全体で統一しましょう」「例外処理の方針を確認しておきましょう」と指摘するのもBSEの仕事。
チームの技術的な共通言語を整備する役割を担います。
3.QC(Quality Control)/QCL(Quality Control Leader)――品質を守る専門職
オフショア開発では、テスト工程にQC(品質管理)とQCL(品質管理リーダー)という専任職種を置くことが一般的です。QCは単体・結合・システムテストの観点を作成し、テストケースを設計・実施します。QCLはその品質を横断的にチェックし、欠陥傾向を分析します。
国内開発では、開発者自身がテストを兼任することが多く、テスト担当を独立させるケースは限られます。しかし、海外チームでは「テストの粒度」や「合格基準」の感覚が異なるため、第三者による品質検証が不可欠です。
特にベトナムでは、日本語での読み書きができるQCメンバーが多く、翻訳を介さずにテストケースやバグ報告を扱えるのが強みです。また、彼らは単にバグを見つけるだけでなく、「再発防止のためにどの設計段階で止められたか」を振り返る文化を持っています。
その結果、テストチーム自体が“品質教育の場”として機能します。
4.QA(Quality Assurance)――プロセス品質を監視する立場
QCが「成果物の品質」を担保するのに対し、QAは「プロセスの品質」を監視します。
各工程が計画どおり実施されているか、レビュー・テストが適切に行われているかを定期的に監査し、問題があれば是正を指示します。
国内の中小規模開発では、QAを専任で置くことは稀です。しかし、オフショアでは国や拠点ごとに複数プロジェクトが同時進行するため、標準化と再現性の確保が成功の鍵になります。
QAはその要となる存在で、チェックリストの運用、品質レポートの作成、振り返りの実施などを通じて、プロジェクト横断で改善を促します。たとえば、過去の案件で発生した障害を横展開し、次の案件では事前チェックに組み込むといったサイクルを構築します。
QAがいることで、属人的な品質管理から脱却できるのです。
5.コミュニケーター/翻訳担当――情報の正確さを担保する支援役
オフショア開発では、BrSEが通訳を兼ねることもありますが、全てを担うのは現実的ではありません。
そこで登場するのが、会議の逐次通訳やドキュメント翻訳を専門に行うコミュニケーターです。
議事録や仕様書、テスト報告書など、正確な翻訳を必要とする文書は膨大です。ここで誤訳が生じると、要件や優先度の認識が狂い、手戻りが発生します。コミュニケーターが存在することで、BrSEやPMが調整業務に専念でき、プロジェクト全体の情報伝達スピードが格段に上がります。
また、最近では翻訳ツールの精度向上により、「機械翻訳+人のレビュー」という効率的な分業も可能になっています。
テキスト量が膨大なオフショア開発では、この役割が地味に大きな成果を生むのです。
6.QAリーダー/PMO――全体最適を見渡す監督者
開発拠点が複数あり、プロジェクトが並行して動く企業では、QAリーダーやPMO(Project Management Office)を置く体制が一般的です。PMOはプロジェクト全体を俯瞰し、進捗・課題・リスクを横断的に管理します。一方でQAリーダーは品質の基準を統一し、複数チーム間で改善サイクルを回します。
オフショア開発では、個々のチームが独立して動くと、品質や管理レベルがバラバラになります。PMOやQAリーダーがいることで、チームをまたぐ共通ルールと透明性を保つことができます。
国内の大手SIerにおける“標準化部門”のような役割を、オフショア体制でも再現するのが理想です。
7.“日本では不要”でも“オフショアでは必要”な理由
これらの職種は、国内開発では「コスト要因」に見えるかもしれません。
しかしオフショア開発においては、距離・言語・文化という3つの壁を越えるための装置です。
BrSEが言語の壁を、BSEが技術の壁を、QC・QAが品質の壁を、それぞれ支えています。
この“装置”がなければ、わずかな誤解が雪だるま式に膨らみ、最終的には「安くない」「早くない」「品質が低い」という結果に陥ります。オフショア成功の鍵は、メンバーを減らすことではなく、必要な役割を適切に配置して協働させることなのです。
まとめ

オフショア開発は単なるコスト削減の手段ではなく、多様な専門性で補い合うチームづくりの取り組みです。国内と同じ感覚で体制を組んでしまうと、すぐに見えない摩擦が発生します。BrSE、BSE、QC、QA、コミュニケーター、PMO――これらの職種は、「距離を埋めるためのコスト」ではなく「信頼を築くための投資」として位置づけるべきです。
オフショア開発を検討する際は、“誰がコードを書くか”だけでなく、“誰が理解をつなぐか”を考えること。そこにこそ、成功するチーム設計の第一歩があります。
メール配信申込みのご案内
ベトナムオフショア開発協会では、
日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。
本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。
セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。