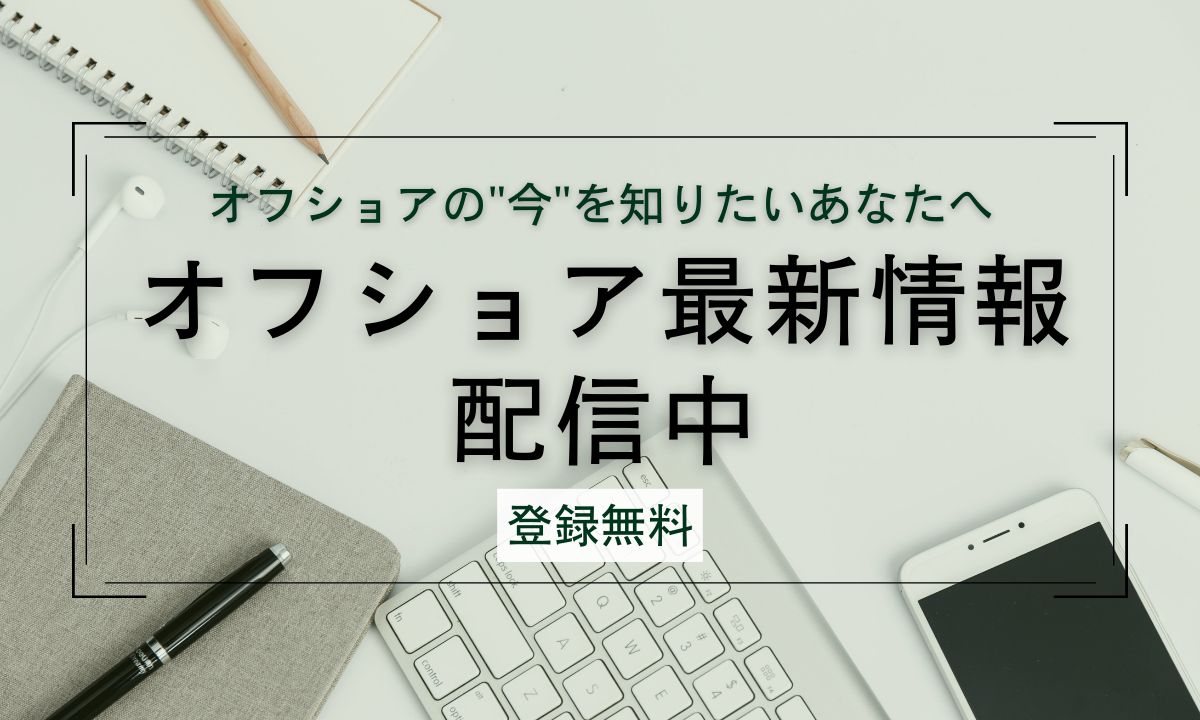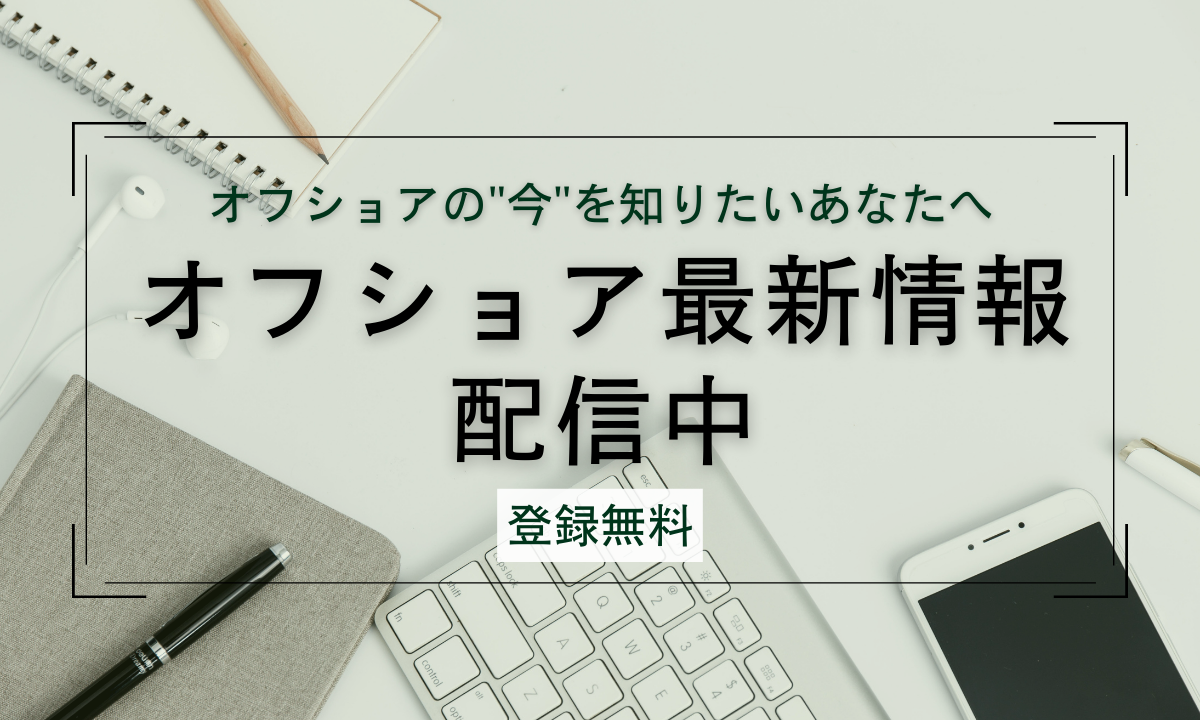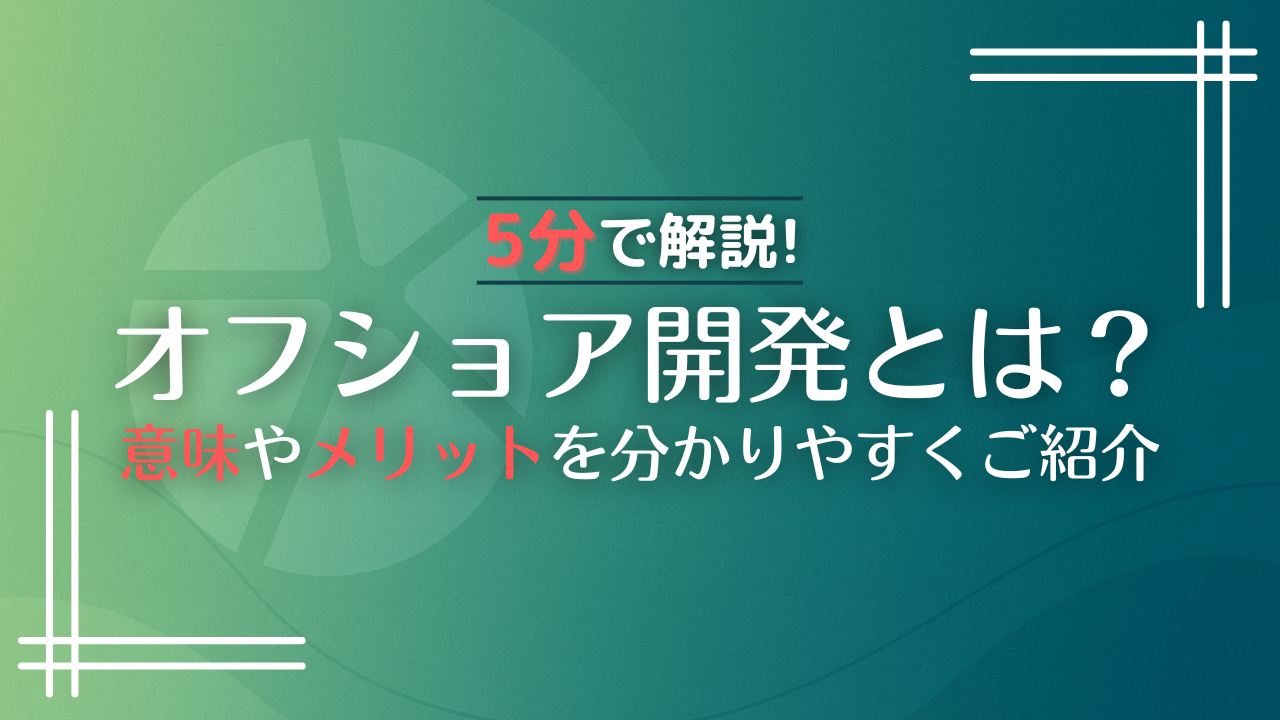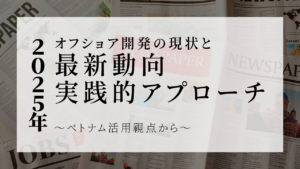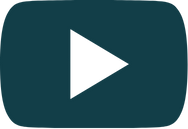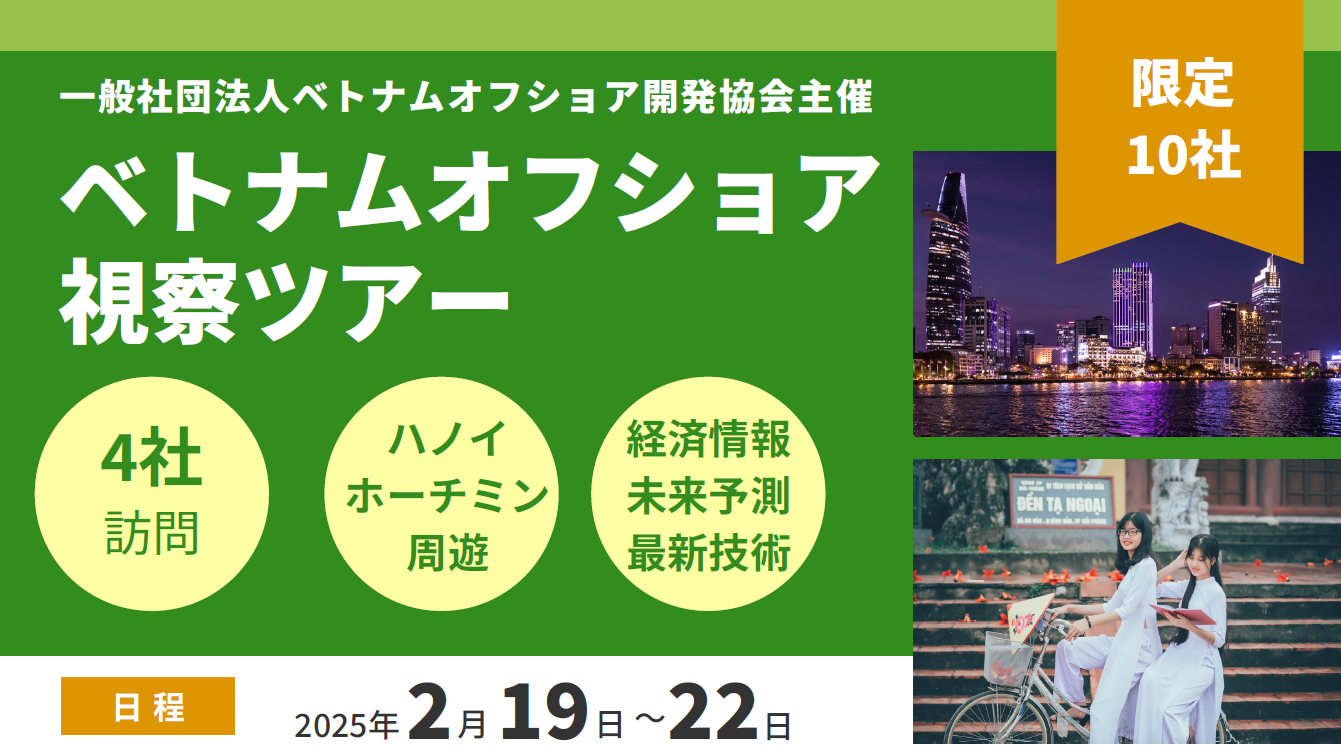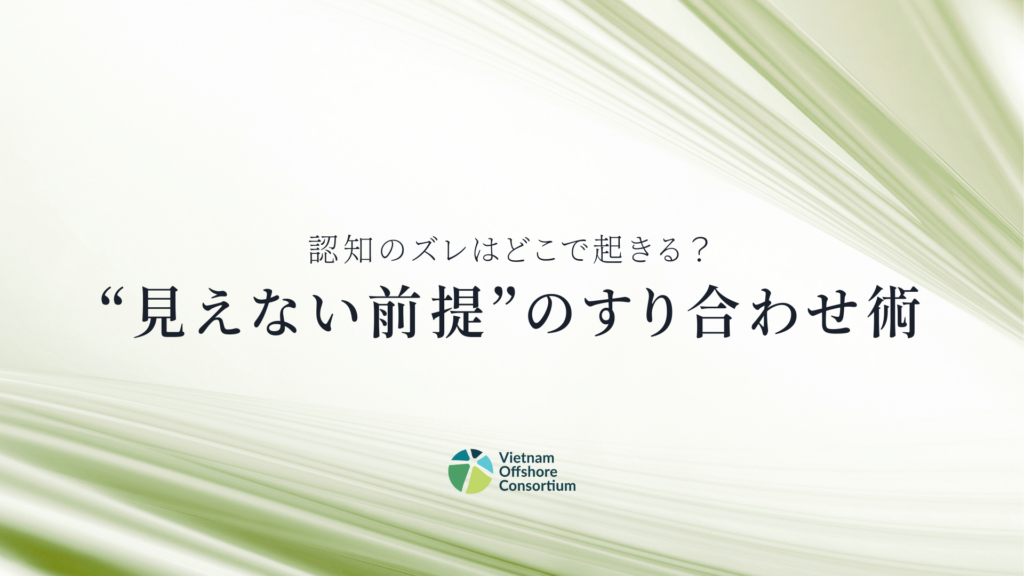
こんにちは。ベトナムオフショア開発協会、理事のLE ANH TUANです。
オフショア開発では、同じ言葉を使って話していても、成果物が期待と大きく異なることがあります。この原因の多くは、「認知のズレ」にあります。
認知のズレとは、双方が無意識に持っている“見えない前提”の違いによって発生する誤解です。
言語や文化、経験の違いによって生まれるこのズレは、プロジェクト後半で手戻りや品質低下を招くことがあります。
この記事では、認知のズレが発生する背景、実例、そしてすり合わせの具体的な方法を詳しく解説します。
この記事はこんな人におすすめです。
1.認知のズレが生まれる背景
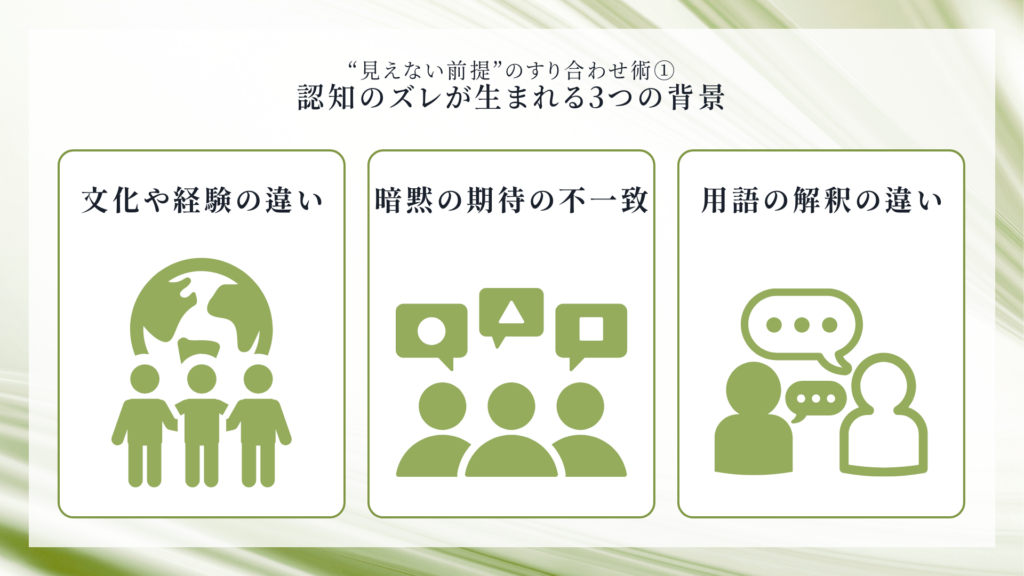
①文化や経験の違い
例えば「テストをしてください」という指示一つでも、日本の開発者は「単体テストから結合テストまで網羅的に行う」と考えるかもしれません。一方、海外チームは「ユニットテスト中心で実施」と解釈することがあります。
どちらも間違いではありませんが、前提が異なるために結果がずれてしまいます。
②暗黙の期待の不一致
日本では「高品質」「納期厳守」は当然の前提として捉える傾向がありますが、海外チームにとっては明示されなければ期待値は共有されません。
このズレが後工程での修正や手戻りを生み、工数とコストを増大させます。
③用語の解釈の違い
同じ言葉でも、文化や業務経験によって理解が異なる場合があります。たとえば「簡単に使えるUI」という表現は、日本側では直感的操作を指しますが、海外チームではデザインがシンプルであることと解釈することがあります。
2.認知のズレを防ぐ具体的手法
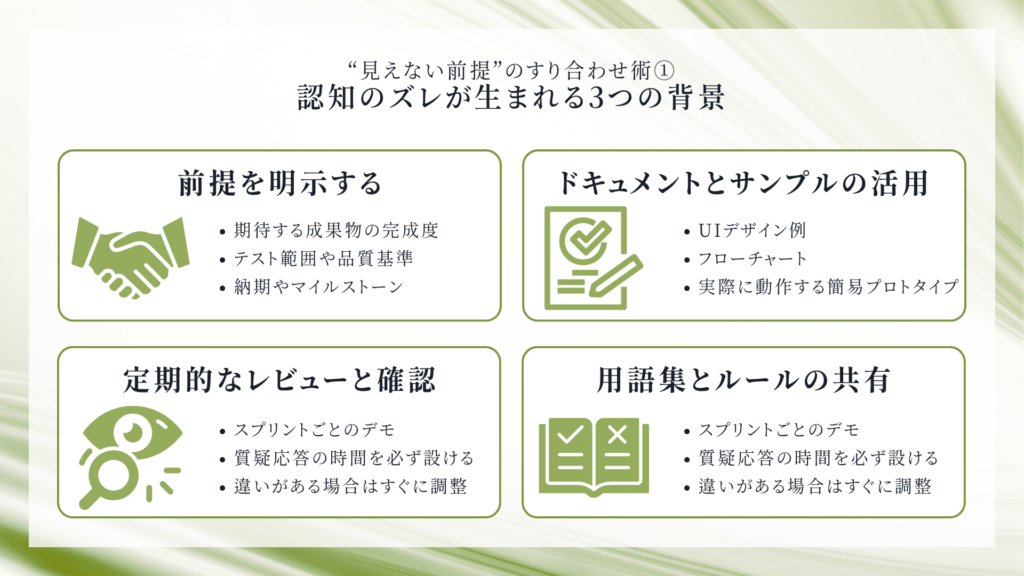
①前提を明示する
プロジェクト開始時に、双方の前提を明確にして共有することが重要です。
- 期待する成果物の完成度
- テスト範囲や品質基準
- 納期やマイルストーン
②ドキュメントとサンプルの活用
仕様書だけでなく、完成イメージやモックアップを提示することで、認識のズレを減らすことができます。
- UIデザイン例
- フローチャート
- 実際に動作する簡易プロトタイプ
③定期的なレビューと確認
進捗に応じて定期的なレビューを行い、早期に認知のズレを発見します。
- スプリントごとのデモ
- 質疑応答の時間を必ず設ける
- 違いがある場合はすぐに調整
④用語集とルールの共有
プロジェクト内で使用する専門用語や略語を整理してチーム全体で共有することで、誤解を防ぎます。
3.実際の事例
ある企業で、「ユーザーが簡単に操作できる検索機能を作る」という依頼を出しました。日本側では直感的な操作と高速検索を想定していましたが、海外チームはUIがシンプルであればよいと解釈してしまい、検索速度の最適化は行われませんでした。
後からこの差異が発覚し、追加工数とコストが発生しました。
このケースでは、初期段階で「操作のしやすさ」「検索速度」の両方を明示して共有していれば防げた問題です。

4.すり合わせを習慣化する
認知のズレは一度の打ち合わせでは解消できません。継続的に確認を行う仕組みが必要です。
- 毎週の定例会議で進捗と認識を確認
- マイルストーンごとのレビューで齟齬を修正
- 疑問点は早期に質問して解消
これにより、プロジェクト後半での大きな手戻りを防ぎ、効率的な開発が可能になります。
まとめ
オフショア開発では文化や経験の違いによって「認知のズレ」が生じやすく、これが手戻りや品質低下の原因になります。
重要なのは、見えない前提を可視化し、定期的にすり合わせることです。
- 前提を明示する
- 成果物のサンプルやドキュメントで共有
- 定期的にレビューして確認
この習慣を取り入れることで、オフショア開発の成功率は大幅に向上します。、プロジェクト後半での大きな手戻りを防ぎ、効率的な開発が可能になります。
次のプロジェクトから、まず「私たちの前提は一致しているか?」を確認することをおすすめします。
LE ANH TUAN(ベトナムオフショア開発協会 理事)
メール配信申込みのご案内
ベトナムオフショア開発協会では、
日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。
本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。
セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。